基本的にはビジネスコンサルタントに必要な資格はありません。
しかし、保有していることで案件の受注、プロジェクトの推進に有利になる資格は存在します。また、資格を取得するため勉強を行う中で、コンサルティングに必要な知識を身につけることができます。
コンサルタントに求められる知識は非常に幅広く、戦略・業務・ITなど支援する領域によって求められる知識も異なります。本記事では支援領域別にビジネスコンサルタントにおすすめの資格をご紹介します。
コンサルの転職ならMyVision(マイヴィジョン)
BCG、マッキンゼー、ATカーニー、アクセンチュア、BIG4など累計支援人数8,000名以上の実績を持つ転職エージェント。過去数千件の面接内容を分析した、独自の「面接対策資料」および「想定頻出問答集」を提供。

全般
まず支援領域にかかわらず、コンサルタントの業務全般において役立つスキルを身につけることができる資格をご紹介します。
ITパスポート
ITパスポートは、ITに関する基礎的な知識を証明する国家資格です。
現代においてITにかかわらずに働いているという人はおそらくほとんどいないと思われます。そのため、すべての人がITを活用する上での基礎的な知識を身につけることが必要となります。
またITパスポートは、ITだけでなく経営全般の基礎知識が問われるため、大学卒業後初めてコンサルタントとして働く人が経営を学ぶ手段として非常に効果的です。資格を持っていること自体が高く評価されるわけではありませんが、IT・経営全般を体系的に学習することができます。
資格の内容
ITパスポート試験では、以下の3つの分野から出題されます。いずれも浅く広く知識が問われるため、一つ一つの分野の理解よりも、網羅的にインプットを行うことが期待されます。
- テクノロジ系:コンピュータやネットワークの仕組み、セキュリティ、データベースなど、ITの基礎技術に関する知識
- マネジメント系:ITプロジェクトの管理、ITサービスの運用、経営戦略におけるITの活用など、ITマネジメントに関する知識
- ストラテジ系:企業と法務、セキュリティ対策、経営戦略、財務・会計など、ITをビジネスに活用するための知識
受験資格
なし
ITパスポート試験には、年齢や学歴などによる受験資格の制限はありません。誰でも受験することができます。そのため、時間があれば学生のうちに取得する
取得難易度
ITパスポート試験は、IT系の国家資格の中では入門レベルとされており、比較的取得しやすい資格と言えます。また、試験はコンピュータを活用したCBT(Computer Based Testing)方式で随時実施しているため、受験もしやすいです。
合格率
51.7%(令和6年4月度~令和6年5月度)
近年のITパスポート試験の合格率は50%前後で推移しています。また、社会人のみでは54.2%となります。
勉強方法
ITパスポートの勉強は、通信講座などもありますが、参考書を購入して勉強することがおすすめです。下記の「よくわかるマスター」はテキストと参考書が一体となっており、本書1冊で合格を目指すことができます。
勉強期間
ITパスポート試験の勉強期間は、個人のIT知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- IT初学者:100時間~180時間
- ITの基礎知識がある方:20時間~50時間
費用
1万円前後
- 受験費用:7,500円
- 参考書:2,000~3,000円
中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業の経営課題を診断し、経営改善のためのアドバイスを行う専門家です。また、中小企業と行政・金融機関等を繋ぐパイプとしての役割、中小企業への施策の適切な活用支援など、非常に幅広い役割があります。
名称としては”中小企業”とついていますが、企業規模に問わず経営に関する幅広い知識を問われます。コンサルタントとして企業を支援する上で、必要な知識を学ぶことができます。
資格の内容
中小企業診断士試験は、1次試験と2次試験に分かれています。
- 1次試験:7科目のマークシート方式で行われ、経営に関する幅広い知識が問われます。
- 企業経営理論
- 財務・会計
- 運営管理
- 経済学・経済政策
- 法務
- 情報システム
- 中小企業経営・中小企業政策
- 2次試験:2日間にわたり、事例問題に対する論述式試験と口頭試問が行われます。実務的な問題解決能力が問われます。
受験資格
なし
中小企業診断士試験には、年齢や学歴などによる受験資格の制限はありません。誰でも受験することができます。一方で、ある程度の実務経験を積まないと理解が難しい論点もあるため、数年の社会人経験があると勉強も進めやすいです。
また、他の資格を保有していることで、受験が免除される科目もあります。
取得難易度
中小企業診断士試験は、広範囲な知識と論述能力が求められるため、難易度は高いと言えます。
合格率
6%(令和5年度)
- 1次試験:29.6%
- 2次試験:18.9%
1次試験の申込から2次試験の合格まで至る割合としては5%前後です。
近年の1次試験の合格率は30~40%前後で推移しています。2次試験の合格率は20%前後で推移しています。
勉強方法
中小企業診断士は独学でも学習することが可能ですが、試験範囲が非常に広範であるため、モチベーションの維持が難しいです。そのため、通信講座などでサポートを受けながら勉強を進めることをおすすめします。
独学で勉強する場合、下記のTACの参考書がおすすめです。各科目の冒頭には学習ガイダンスがあり、要点を確認しながら学習を進めることができます。
勉強期間
中小企業診断士試験の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- 初学者: 800時間~1,000時間
- 経営学の知識がある方: 600時間~800時間
費用
15~20万円前後
- 受験費用:14,500円
- 通信講座:15万円前後
日商簿記2級
日商簿記2級は、企業の経理担当者として必要な商業簿記・工業簿記(原価計算を含む)の知識を証明する資格です。企業の財務諸表を理解し、経営状況を分析、意思決定をサポートするために求められるレベルとなります。ビジネスコンサルタントであれば2級レベルの知識があれば、財務分析に基づくコンサルティングを行うことができます。
資格の内容
日商簿記2級試験は、以下の2つの分野から出題されます。
- 商業簿記: 株式会社の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など)の作成、決算整理、財務諸表分析などに関する知識
- 工業簿記: 製造業における原価計算(実際原価計算、標準原価計算など)に関する知識
受験資格
なし
日商簿記2級試験には、年齢や学歴などによる受験資格の制限はありません。
取得難易度
日商簿記2級試験は、簿記3級の知識を前提としており、難易度が高いと言えます。合格率は20%~30%程度で推移していますが、回によって変動が大きいため、難易度は一定ではありません。
合格率
15.5%(166回(2024年2月25日))
近年の合格率は15%~30%程度で推移しています。
勉強方法
簿記初学者の場合、最初は内容を正確に理解するため以下のようなサイトで講義を受講することをおすすめします。経理実務の学校では一部コンテンツは無料で閲覧することができます。
すでに簿記3級を取得している方やある程度の簿記の知識がある方であれば、参考書による独学でも合格レベルに
勉強期間
日商簿記2級試験の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- 簿記初学者: 300時間~500時間
- 簿記3級合格者: 150時間~250時間
費用
5万円前後
- 受験費用:5,500円
- 通信講座:3万円前後
- 参考書:1万円前後
TOEIC
TOEIC (Test of English for International Communication) は、英語によるコミュニケーション能力を測る世界共通のテストです。主に「聞く」「読む」能力を測るTOEIC Listening & Reading Testと、「話す」「書く」能力を測るTOEIC Speaking & Writing Testsがあります。
ビジネスコンサルタントであれば、TOEIC Listening & Reading Testにおいて800点以上のスコア取得を目指したいです。英語の文献を調査したり、英語でのレポート作成を行う機会もあるため、ある程度のレベルの英語力が求められます。
資格の内容
TOEIC Listening & Reading Testは、リスニングセクション(約45分間・100問)とリーディングセクション(75分間・100問)の2つのセクションから構成されています。問題は全て選択式で、日常生活やビジネスシーンにおける幅広い英語力を測ることができます。
受験資格
なし
TOEIC Listening & Reading Testには受験資格の制限はありません。
取得難易度
- 600点以上:
- 800点以上:
- 900点以上:
スコア500点以上が中学・高校で学習する英語の理解があれば、取得できるレベルです。ビジネスコンサルタントであれば、スコア800点以上取得が一つの目標となります。800点あれば、単語などを調べながらにはなりますが、不自由なく読み書きを行うことができます。
勉強方法
勉強方法は基本的には公式問題集を解くことが最も効率的です。TOEICでは、単語や文法の理解の他、問題形式、出題の傾向を理解しておくことで高得点を狙うことができます。
勉強期間
TOEIC Listening & Reading Testの勉強期間は、目標スコアや現在の英語力によって異なります。以下、中学・高校で学習する内容がある程度理解できているレベルを基準とすると目安は、以下の通りです。
- 600点以上:200~250時間
- 800点以上:400~450時間
- 900点以上:550~600時間
費用
1~1.5万円前後
- 受験費用:7,810円(税込)
- 参考書:5,000円前後
戦略
戦略領域においては明確に求められる資格はありません。しかし、戦略領域においては定量的な分析が求められるため、基礎的な統計に関する知識があると望ましいです。また、経営のエキスパートとしてMBAの学位があると高く評価されます。
統計検定2級
統計検定2級は、大学基礎課程(1・2年次学部共通)レベルの統計学の知識と活用能力を問う試験です。統計検定の中でも、統計の基礎知識を身につけるための最初のステップとして位置付けられています。
資格の内容
統計検定2級では、以下の内容が出題されます。
- 記述統計:データの収集・整理・要約、代表値、散布度、相関、回帰分析など
- 確率分布:確率、確率変数、離散型確率分布、連続型確率分布、正規分布など
- 推測統計:標本抽出、推定、検定、区間推定、仮説検定など
受験資格
なし
統計検定2級には、年齢や学歴などによる受験資格の制限はありません。
取得難易度
統計検定2級は、大学基礎統計学の知識と問題解決力が求められるため、統計学の初学者にとってはやや難易度が高いといえます。
合格率
49.1%(2023年)
合格率は50%前後で推移しています。
勉強方法
統計検定2級は、基本的には公式テキストと問題集で勉強することをおすすめします。問題集には過去問も収録されているので、過去問を解きながら問題の傾向を把握しつつ、自身の苦手な論点を克服していきましょう。
勉強期間
統計検定2級の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- 統計学初学者:100~120時間
- 統計学の基礎知識がある方:60~80時間
費用
1~1.5万円前後
- 受験費用:7,000円(税込)
- 参考書:5,000円前後
MBA
MBA(Master of Business Administration)は資格ではなく学位ですが、戦略系コンサルティングファームにおいて特に評価される資格です。経営戦略、マーケティング、ファイナンス、会計など、ビジネスに必要な幅広い知識を身につけることができます。海外のMBAであれば、英語力も併せて鍛えることができます。
取得には2年間ビジネススクールに通い、修士課程を修了する必要があるため、戦略系コンサルティングファームでパートナークラスを目指すという強い意志のある方におすすめします。
資格の内容
MBAプログラムは、大学院によって異なりますが、一般的には以下の内容が含まれます。座学だけではなく、ケーススタディでディスカッションを行う機会も多いため、総合的な思考力が磨かれます。
- コア科目:経営戦略、マーケティング、ファイナンス、会計、組織行動学など、経営学の基礎となる科目を学びます。
- 選択科目:各自の興味やキャリア目標に合わせて、特定の分野を深く学ぶことができます。
- ケーススタディ:実際の企業の事例を分析し、問題解決能力を養います。
- グループワーク:チームで課題に取り組み、コミュニケーション能力やリーダーシップを養います。
- インターンシップ:企業で実務経験を積むことで、実践的なスキルを身につけることができます。
- 修士論文:研究テーマを設定し、論文を執筆することで、研究能力を養います。
受験資格
MBAプログラムの受験資格は、大学院によって異なりますが、一般的には以下の条件を満たす必要があります。
- 学士号:大学卒業またはそれと同等の学力があると認められること
- 職務経験:数年以上の職務経験があること(大学院によっては不要な場合もあります)
- 英語力:英語圏の大学院の場合は、TOEFLやIELTSなどの英語試験で一定のスコアを取得する必要があります。
また、大学院に入学するためにはMBA入試に合格する必要があります。入試の科目は大学院によって異なりますが、大きく以下の2パターンに分けられます。自身の志望する大学院の科目を確認し、準備を行う必要があります。
- 筆記試験(小論文)、書類選考、面接
- 筆記試験はなく、書類選考、面接だけ
取得難易度
MBAプログラムの取得難易度は、大学院によって異なりますが、入学後は継続的な学習を行わなければ修了することは難しいです。
合格率
100%近く
一般的にMBAは、入学後しっかりと履修科目の単位を取得していれば100%に近い割合で取得できるとされています。
勉強期間
2年間
MBAプログラムの期間は、大学院によって異なりますが、一般的には2年間です。働きながら履修する方も多いため、単位を取得するのにさらに時間を要する場合もあります。
費用
- 国内MBA:100~300万円前後
- 海外MBA:800~1,500万円前後
MBAプログラムの費用は、大学院によって大きく異なります。海外MBAで現地に滞在する場合は生活費や家賃なども必要となるため、1,000万円近く必要となる場合もあります。
IT・PMO
ビジネスコンサルタントはIT戦略策定、システム開発プロジェクトに従事することもあります。そのため、システム・ソフトウェア開発に関する基礎的な知識を身につけておくことが期待されます。また、PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)として、プロジェクトの管理を支援することもあります。
応用情報技術者試験
応用情報技術者試験は、情報処理推進機構(IPA)が主催する国家試験「情報処理技術者試験」の一つです。ITを活用した戦略策定、システムの企画・要件定義、サービスの安定的な運用を行う者に期待される知識が問われます。システム開発の上流から下流までの一連のプロセスと専門用語を網羅的に理解することができます。
資格の内容
応用情報技術者試験では、以下の分野から出題されます。
- テクノロジ系:コンピュータシステム、技術要素、開発技術、データベース、ネットワーク、セキュリティなど、ITの基礎技術に関する知識
- マネジメント系:プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント、システム監査など、ITシステムの開発・運用・管理に関する知識
- ストラテジ系:システム戦略、経営戦略、企業と法務、情報セキュリティマネジメントなど、ITをビジネスに活用するための知識
試験は午前と午後に分かれており、午前は多岐選択式、午後は記述式で出題されます。
受験資格
なし
応用情報技術者試験には、年齢や学歴などによる受験資格の制限はありません。
取得難易度
応用情報技術者試験は知識レベルはそれほど高くはありませんが、記述式の試験があるため、丸暗記だけでは合格はできません。問題文を理解する力と設問に対応するキーワードを適切に活用する力が求められます。
合格率
27.2%(令和5年度春季)
近年の合格率は20~30%前後で推移しています。
勉強方法
応用情報技術者試験の勉強方法は基本的には参考書を用いた学習となります。基本情報技術者試験に合格していない場合は、まずは基本情報技術者試験のテキストを用いて基礎知識を身につけましょう。
すでに基本情報技術者試験に合格している場合は、問題集の演習から開始しましょう。出題は過去問からの流用も多いため、過去問の演習も行うことをおすすめします。
勉強期間
応用情報技術者試験の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- IT初学者:300時間~500時間
- 基本情報技術者試験合格者:100時間~200時間
費用
1~1.5万円前後
- 受験費用:7,500円(税込み)
- 参考書:5,000円前後
ITストラテジスト試験
ITストラテジスト試験は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施する国家試験です。経営戦略に基づきIT戦略を策定し、業務改革や製品・サービスの企画・推進を主導する人材に求められる知識が問われます。ITコンサルタントは企業のIT戦略策定を支援することが多いため、プロジェクトにおいて評価されます。
資格の内容
ITストラテジスト試験は、以下の能力を評価します。
- 経営戦略に基づいたIT戦略の立案能力
- ビジネスモデルの分析・評価能力
- IT投資対効果の評価能力
- ITプロジェクトの企画・管理能力
- ITを活用した業務改革の推進能力
試験は、午前I、午前II、午後I、午後IIの4つの試験区分で構成されています。午前Iと午前IIは多肢選択式、午後Iは記述式、午後IIは論述式です。
受験資格
なし
ITストラテジスト試験には、年齢や学歴などによる受験資格の制限はありませんが、応用情報技術者試験を合格していれば、午前Iの受験が2年間免除されます。
取得難易度
ITストラテジスト試験は、高度IT人材向けの試験であるため、難易度は比較的高いです。また、実務経験がないと理解が難しい問題も多いため、ある程度実務経験を積んだ上で受験することをおすすめします。
合格率
15.5%(令和5年度春季)
近年の合格率は15%前後で推移しています。
勉強方法
ITストラテジスト試験の勉強方法は基本的には参考書を用いた学習となります。基本情報技術者試験に合格していない場合は、まずは基本情報技術者試験のテキストを用いて基礎知識を身につけましょう。午後IIは論述式の試験であるため、問題集を活用し、キーワードの押さえ方、文章の書き方を繰り返し練習しましょう。
勉強期間
ITストラテジスト試験の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- IT初学者:800~1,000時間
- 応用情報技術者試験合格者:300~500時間
- IT領域の実務経験者:300~500時間
費用
1~1.5万円前後
- 受験費用:7,500円(税込み)
- 参考書:5,000円前後
プロジェクトマネージャ試験
プロジェクトマネージャ試験は、情報処理推進機構(IPA)が主催する国家試験「情報処理技術者試験」の一つです。ITプロジェクトの計画、実行、管理を統括するプロジェクトマネージャに求められる知識と能力を評価する試験です。
ビジネスコンサルタントはPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)として、システム開発プロジェクトのマネジメントを支援することが多いです。本試験に合格していることで、クライアントへのアピールになったり、案件の受注確率を高めることができます。
後述するPMPと比較して受験資格が不要で、資格の更新もないため取得・維持しやすい資格です。一方でグローバルでの認知度は劣ります。
資格の内容
プロジェクトマネージャ試験では、以下の分野から出題されます。
- プロジェクトの立ち上げ・計画
- プロジェクトの実行・管理
- プロジェクトの終結
試験は午前I、午前II、午後I、午後IIの4つの試験区分で構成されています。午前Iと午前IIは多肢選択式、午後Iは記述式、午後IIは論述式です。
受験資格
なし
プロジェクトマネージャ試験には、年齢や学歴などによる受験資格の制限はありませんが、応用情報技術者試験を合格していれば、午前Iの受験が2年間免除されます。
取得難易度
プロジェクトマネージャ試験は、高度IT人材向けの試験であるため、難易度は比較的高いです。また、実務経験がないと理解が難しい問題も多いため、ある程度実務経験を積んだ上で受験することをおすすめします。
合格率
13.5%(令和5年度秋季)
近年の合格率は15%前後で推移しています。
勉強方法
プロジェクトマネージャ試験の勉強方法は基本的には参考書を用いた学習となります。基本情報技術者試験に合格していない場合は、まずは基本情報技術者試験のテキストを用いて基礎知識を身につけましょう。午後IIは論述式の試験であるため、問題集を活用し、キーワードの押さえ方、文章の書き方を繰り返し練習しましょう。
勉強期間
プロジェクトマネージャ試験の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- IT初学者:800~1,000時間
- 応用情報技術者試験合格者:300~500時間
- IT領域の実務経験者:300~500時間
費用
1~1.5万円前後
- 受験費用:7,500円(税込み)
- 参考書:5,000円前後
PMP
PMP(Project Management Professional)は、米国PMI(Project Management Institute)が認定する国際的なプロジェクトマネジメント資格です。プロジェクトマネジメントに関する知識や経験を有することを証明し、プロジェクトマネージャーとしての能力を客観的に評価することができます。
プロジェクトマネジメントのグローバルスタンダードとしての地位を確立しており、前述のプロジェクトマネージャ試験よりも高く評価される傾向にあります。企業が採用時に優遇したり、国の入札案件でも要件となったりと価値が認められています。
資格の内容
PMP試験は、PMIが発行するプロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)に基づいて出題されます。試験内容は、プロジェクトマネジメントのプロセス群(開始、計画、実行、監視・コントロール、終結)と知識エリア(統合、スコープ、スケジュール、コスト、品質、資源、コミュニケーション、リスク、調達、ステークホルダー)に関する知識を問うものです。
受験資格
PMP試験の受験資格は以下の2つの条件を満たす必要があります。
- プロジェクトマネジメント経験
- 【高卒・短大者の場合】プロジェクト業務を指揮・監督する立場で、60ヶ月のプロジェクトマネジメント経験
- 【大卒者の場合】プロジェクト業務を指揮・監督する立場で、36ヶ月のプロジェクトマネジメント経験
- 研修の受講
- 35時間の公式なプロジェクトマネジメントの研修の受講
取得難易度
PMP試験は、プロジェクトマネジメント経験が求められるため比較的取得難易度が高いです。試験に関しては出題の傾向を理解すれば対策はしやすいです。
合格率
不明
PMP試験の合格率は、公式には公表されていませんが、一般的には60%前後と言われています。
勉強方法
基本的には、PMPの受験対策講のテキスト・問題集を使用して学習を行います。ただし、講座で用意されているテキストは日本語が不自然であったりと分かりづらいことがあります。
日本語でPMBOKの体系を正確に理解するため、下記のような日本語の参考書を適宜参照するのも効果的です。複雑なPMBOKの内容がわかりやすく図解されており、概要を理解する上で非常に役に立ちます。
勉強期間
80~100時間前後
- プロジェクトマネジメント講座:35時間
- 自学自習:50時間
費用
15~20万円
- 受験費用:PMI会員: 405米ドル/非会員: 555米ドル
- 講座受講:7~10万円
- 参考書:5,000円
会計
公認会計士
公認会計士は、会計・簿記のエキスパートとして、企業の財務諸表を監査し、その適正性を保証する専門家です。会計・財務・経営全般に関する高度な知識が求められます。公認会計士としての知識は監査だけでなく、M&Aや事業再生といったコンサルティングの分野でも活用することができます。もちろん資格がなくともコンサルティングは可能ですが、公認会計士の資格を保有していればクライアントからの信頼を得ることができます。
資格の内容
公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験の2段階に分かれています。
- 短答式試験:財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目から出題されます。
- 論文式試験:会計学、監査論、企業法、租税法に加えて選択科目(経営学・経済学・民法・統計学)から出題されます。9割以上の受験生は経営学を選択しています。
論文式試験では、知識だけでなく思考力・問題解決能力、公認会計士としての実務適性が評価されます。
受験資格
なし
公認会計士試験には、年齢や学歴などによる受験資格の制限はありません。他の資格による試験の免除もありますが、いずれもハードルが高いので、通常通り全科目受験して合格するのが効率的です。
取得難易度
公認会計士試験は、非常に難易度が高い試験として知られています。合格率は10%前後で推移しており、広範囲な専門知識と深い理解、応用力が求められます。
合格率
7.6%(令和5年公認会計士試験)
近年の合格率は10%前後で推移しています。
勉強方法
公認会計士試験は試験範囲も広く、各論点を深く理解していないと回答が難しい問題も多いので、講座を受講することをおすすめします。以下の講座はサポートも充実しているため、初学者でも安心して学習を進めることができます。
勉強期間
公認会計士試験の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- 初学者:2,000時間~3,000時間
- 会計学の知識がある方:1,000時間~2,000時間
費用
70万円~80万円前後
- 受験費用:19,500円
- 講座受講:70~80万円
米国公認会計士(USCPA)
USCPA (U.S. Certified Public Accountant) は、アメリカ各州が認定する公認会計士の資格です。米国会計基準に基づく会計処理などを学ぶため、日本での独占業務ができるわけではありませんが、Big4などの外資系コンサルティングファームにおいては有利に働きます。また、英語で学習を行うため、ビジネスに関する英語を身につけるのにも役立ちます。
資格の内容
USCPA試験は、以下の4つの必須科目と選択科目1科目から構成されています。
必須科目
- FAR (Financial Accounting and Reporting):財務会計および報告に関する知識
- AUD (Auditing and Attestation):監査および証明業務に関する知識
- REG (Regulation):法規制(税法、商法など)に関する知識
選択科目
- BAR(Business Analysis and Reporting):ビジネス分析及び報告
- ISC(Information Systems and Controls):情報システム及び統制
- TCP(Tax Compliance and Planning):税法遵守及び税務計画
各科目の試験は、コンピューターベーステスト(CBT)形式で実施され、年間を通じて受験することができます。
受験資格
USCPA試験の受験資格は、各州によって異なりますが、一般的には以下の条件を満たす必要があります。
- 学位要件:4年制大学卒業またはそれと同等の学力があること
- 単位要件: 会計単位とビジネス単位を一定以上取得していること
取得難易度
USCPA試験は受験資格を満たすため単位の取得が必要となります。また、米国会計基準は日本の会計基準と異なる点も多いため、理解するのにも時間を要する場合もあります。
合格率
52.8%(2022年時点全世界の受験生)
USCPA試験の合格率は、2022年時点で世界中を対象とした受験者全体の平均で52.8%、日本人に限定すると2019年で41.2%となっています。
勉強方法
USCPAでは学歴要件の他、単位要件を満たす必要があるため、単位を取得しながら勉強ができる講座をおすすめします。下記のアビタスでは、受講期間が5年と長めに設定されているため、働きながらでも学習することができます。日本語教材も充実しており、英語が苦手な方でも始めやすいです。
勉強期間
USCPA試験の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- 1,200~1,500時間
費用
80~100万円
- 受験費用:1科目当たり$344.80~$364.80
- 講座受講:60~80万円
AI
近年、企業においてAIの活用が進んでおり、AIをビジネスにどのように適用するかという点が問われます。ビジネスコンサルタントも上流の戦略策定から下流の実装するフェーズまで支援する機会も増えています。そこでAIに関する資格を保有しているとプロジェクトにおいて評価されやすくなります。
G検定
G検定(ジェネラリスト検定)は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する資格試験です。ディープラーニングの基礎知識を有し、適切な活用方針を決定して、事業活用する能力や知識を問われます。G検定を学習することで、AIにできること、AIの活用領域などを理解することができます。
資格の内容
G検定は、ディープラーニングに関する幅広い知識が問われます。試験範囲は、以下の通りです。
- 人工知能(AI)とは
- 機械学習の基礎
- ディープラーニングの概要
- ディープラーニングの手法
- ディープラーニングの応用
- 最新のディープラーニング技術
受験資格
なし
G検定には、年齢や学歴などによる受験資格の制限はありません。
取得難易度
G検定の難易度は比較的易しく、テキストに基づき基礎知識をしっかりと学習すれば合格可能です。
合格率
73.46%(2024年 第3回 G検定)
G検定の合格率は、毎回65%~70%前後で推移しています。
勉強方法
G検定の勉強方法は、基本的には参考書による学習を行います。日本ディープラーニング協会が出版・監修している下記3つの参考書を理解できれば、合格レベルまで達することができます。
勉強期間
G検定の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- 30~40時間
費用
2万円前後
- 受験費用:13,200円
- 参考書:7,000円前後
E資格
E資格は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する、ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力を持つエンジニアを認定する資格です。ビジネスコンサルタントでE資格レベルの知識が問われることは少ないですが、実際の実装まで関与する場合は専門知識を保有していると競争力を持つことができます。
資格の内容
E資格では、以下の分野の知識とスキルが問われます。
- 数学的基礎:線形代数、微積分、確率・統計、情報理論
- 機械学習:回帰、分類、クラスタリング、次元削減、強化学習
- 深層学習:畳み込みニューラルネットワーク (CNN)、再帰型ニューラルネットワーク (RNN)、深層強化学習、自然言語処理、画像認識
- 開発・運用環境:Python、TensorFlow/PyTorch、GPU、クラウド環境、MLOps
受験資格
E資格を受験するには、以下の条件を満たす必要があります。
- JDLA認定プログラムの修了:JDLAが認定した講座を受講し、試験日の過去2年以内に修了していること
取得難易度
E資格は、ディープラーニングに関する高度な知識と実装能力が求められるため、難易度は非常に高いと言えます。
合格率
72.61%(E資格2024#1)
E資格の合格率は、70%前後で推移しています。一見合格率は高く見えますが、受験者のすべてがJDLA認定プログラムを修了しており、一定程度の知識と経験を保有しているからと考えられます。
勉強方法
E資格はJDLA認定プログラムを受講し、学習を進めていきます。グループワーク・ハンズオンなどを取り入れている講座もあるため実践的に学習することができます。
また、試験直前では下記の問題集を活用して対策しても良いと思います。
勉強期間
E資格の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- 200~300時間
費用
10~20万円前後
- 受験費用:一般33,000円/JDLA会員27,500
- 講座受講:5万~17万円(教育訓練給付制度活用で費用を抑えることができます)
システム・クラウドサービス
ビジネスコンサルタントはシステム導入プロジェクトに関与する機会も多いです。その中で、各製品の知識を有していれば、クライアントから高い評価を得ることができます。ただし、ソリューションや製品は非常に多岐にわたるため、まずは主要な製品の知識を身につけることで、汎用性高く活用することができます。
ERPパッケージの領域ではSAPが、クラウドサービスの領域ではAWSが、世界トップのシェアを誇っておりますので、まずはこの2製品に関する資格取得を目指すことをおすすめします。
SAP認定コンサルタント資格(SAP Certified Application Associate)
SAP認定コンサルタント資格は、ドイツのソフトウェア企業SAP SEが提供するソフトウェアのスキルと知識を証明するための資格です。SAPは、企業資源計画(ERP)ソフトウェアの分野で世界でトップのシェアを誇っており、導入プロジェクトに関与する機会も多いと考えられます。
特にSAP Certified Application Associateは、SAPの特定の製品やソリューションに関する基礎知識とスキルを証明する資格です。SAPの導入・運用に関わるコンサルタントが保有することで、クライアントから高い評価を得ることができます。
SAP認定コンサルタント資格には、SAP Certified Development Associateというプログラマーを対象とした資格、SAP Certified Technology Associateというインフラエンジニアを対象とした資格もありますが、ビジネスコンサルタントにはあまり求められないスキルであるため、取得の必要はあまりないといえます。

資格の内容
SAP Certified Application Associateは、SAPの多岐にわたるソリューション領域ごとに、さまざまな資格が用意されています。例えば、以下のような資格があります。
- SAP Certified Application Associate – SAP S/4HANA for Financial Accounting Associates
- SAP Certified Application Associate – SAP S/4HANA Sales 1909
- SAP Certified Application Associate – SAP SuccessFactors Employee Central 1H/2020
各資格は、特定のSAP製品やソリューションに関する知識とスキルを問うもので、試験範囲は各資格によって異なります。現在どのような認定試験が提供されているかは下記サイトに掲載されています。自身が関与するプロジェクトで使用する製品などを確認の上、受験する試験を選択しましょう。
受験資格
原則なし
SAP Certified Application Associateの受験資格は、特にありませんが、プロフェッショナルレベルでは実務経験が求められることがあります。
取得難易度
SAP Certified Application Associateの難易度は資格の種類によって異なりますが、一般的には、SAPの基礎知識があれば取得しやすいです。試験によっては製品の内容が深く問われるため、実務経験がないと回答が難しい問題もあります。
合格率
不明
SAP認定資格の合格率は、公式には公表されていません。
勉強方法
SAP社が提供するSAP Learning Hubを受講するのが、最も効率的で、正確に理解を深めることができます。内容は英語なので、ある程度の英語力は身につけた上で受講することをおすすめします。
初学者の場合、初めに日本語の書籍でSAPの全体像を確認することをおすすめします。
勉強期間
1科目当たり30~40時間
受験する試験の種類にもよりますが、SAP Learning Hubの講義の受講と併せて1科目当たり30~40時間程度が目安となります。
費用
20万円前後
- 受験費用:5~10万円
- 講義受講:5~10万円
SAP認定資格の受験費用は、資格の種類によって異なります。一般的には、1科目あたり5万円~10万円程度です。
AWS認定クラウドプラクティショナー
AWS認定資格は、Amazon Web Services, Inc(AWS)が提供するクラウドサービスに関する知識・スキルを証明する資格です。資格には、基礎コース、アソシエイト、プロフェッショナル、専門知識の4つのカテゴリーがあり、AWS認定クラウドプラクティショナーは基礎コースに該当します。
AWS認定クラウドプラクティショナーでは、AWSの主要なサービスやユースケース、請求と料金モデル、セキュリティの基礎知識などを問われます。また、クラウドを利用したビジネスと従来のITビジネスの違いなどに関しても問われます。
資格の内容
AWS認定クラウドプラクティショナー試験では、以下の分野から出題されます。
- クラウドの概念:クラウドコンピューティングの定義やメリット、AWSクラウドの価値提案など
- セキュリティとコンプライアンス:AWSのセキュリティ対策、共有責任モデル、コンプライアンスに関する知識
- テクノロジー:AWSの主要サービス(コンピューティング、ストレージ、データベース、ネットワークなど)の機能や特徴
- 料金と請求:AWSの料金モデル、コスト最適化の方法など
- AWSのサポート:AWSのサポートプラン、ドキュメント、コミュニティなど
受験資格
なし
AWS認定クラウドプラクティショナー試験には、年齢や学歴などによる受験資格の制限はありませんが、6ヶ月程度の実務経験者を想定されています。
取得難易度
AWS認定クラウドプラクティショナー試験は、AWS認定資格の中では入門レベルとされており、比較的取得しやすい資格です。
合格率
不明
AWS認定クラウドプラクティショナー試験の合格率は、公式には公表されていません。
勉強方法
基本的には、参考書を活用した独学で合格レベルに達することができます。下記のテキストを用いて基礎的な知識をインプットします。
テキストを一通り理解したら、下記の問題集を活用して知識の定着を図ります。
【CLF-C02版】この問題だけで合格可能!AWS 認定クラウドプラクティショナー 模擬試験問題集(6回分390問)
勉強期間
AWS認定クラウドプラクティショナー試験の勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
- AWS初学者:30~50時間
- ITの基礎知識がある方:20~30時間
費用
2万円前後
- 受験費用:100米ドル
- 参考書:1万円前後
IPO
機会は少ないかもしれませんが、コンサルタントとして企業の上場を支援するIPOコンサルティングを行う場合もあります。その際、上場準備の実務に必要な知識を身につけておけば、クライアントに対して高いバリューを発揮することができます。
IPO実務検定 上級レベル
IPO実務検定の上級レベルは、企業の上場準備における、より専門的な知識と応用力を評価する試験です。上級レベルより下の標準レベルの試験もありますが、企業の経営層と対話するコンサルタントであれば、上級レベルまで取得しておくことが望ましいです。
資格の内容
IPO実務検定の上級レベルでは、標準レベルの内容をベースに、より実践的な知識や応用力が問われます。具体的には、以下の内容が出題されます。
- 上場準備の全体像:IPOプロセス全体の流れ、上場審査基準、資本政策、事業計画、証券会社との交渉など
- 実務的な課題解決能力:実際のIPO事例に基づいた問題解決能力、リスク管理、コンプライアンス対応など
- 記述式問題:上記の内容に関する論述問題が出題され、論理的な思考力や表現力が問われます。
受験資格
IPO実務検定の上級レベルを受験するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- IPO実務検定(標準レベル)に合格していること
- 上場準備の実務経験が3年以上あること(自己申告制)
取得難易度
IPO実務検定の上級レベルは、標準レベルよりも難易度が高く、記述式の問題も含まれます。しかし、テキストや問題集、ケーススタディ集などをきちんとやり込めば十分に合格レベルを狙うことができます。
合格率
60%前後
標準レベル、上級レベルともに合格率は60%前後で推移しています。
勉強方法
基本的には、公式テキスト、問題集を用いた学習をおすすめします。すでに標準レベルを合格している場合は、問題集から取り組み、記述式問題は「IPO実践ケーススタディ」で対策を行います。
勉強期間
IPO実務検定の上級レベルの勉強期間は、個人の知識や学習ペースによって異なりますが、標準レベルを合格している場合、目安としては以下の通りです。
- 50~70時間
費用
3万円前後
- 受験費用:20,900円(税込み)
- 参考書:7,000円前後
コンサルの転職ならMyVision(マイヴィジョン)
BCG、マッキンゼー、ATカーニー、アクセンチュア、BIG4など累計支援人数8,000名以上の実績を持つ転職エージェント。過去数千件の面接内容を分析した、独自の「面接対策資料」および「想定頻出問答集」を提供。

まとめ
この記事では、戦略、IT、会計、AI、システム・クラウドサービス、IPOといった、さまざまな支援領域で活躍するビジネスコンサルタントにとっておすすめの資格を紹介しました。
資格を取得することでクライアントから高い評価を得られるとともに、取得の過程で知識・スキルを身につけることができます。資格取得は、専門知識やスキルを証明するだけでなく、コンサルタントとしての市場価値を高め、キャリアアップや独立開業にもつながる可能性があります。ぜひこの記事を参考に、自分に合った資格に挑戦し、ビジネスコンサルタントとしてのさらなる成長を目指しましょう。
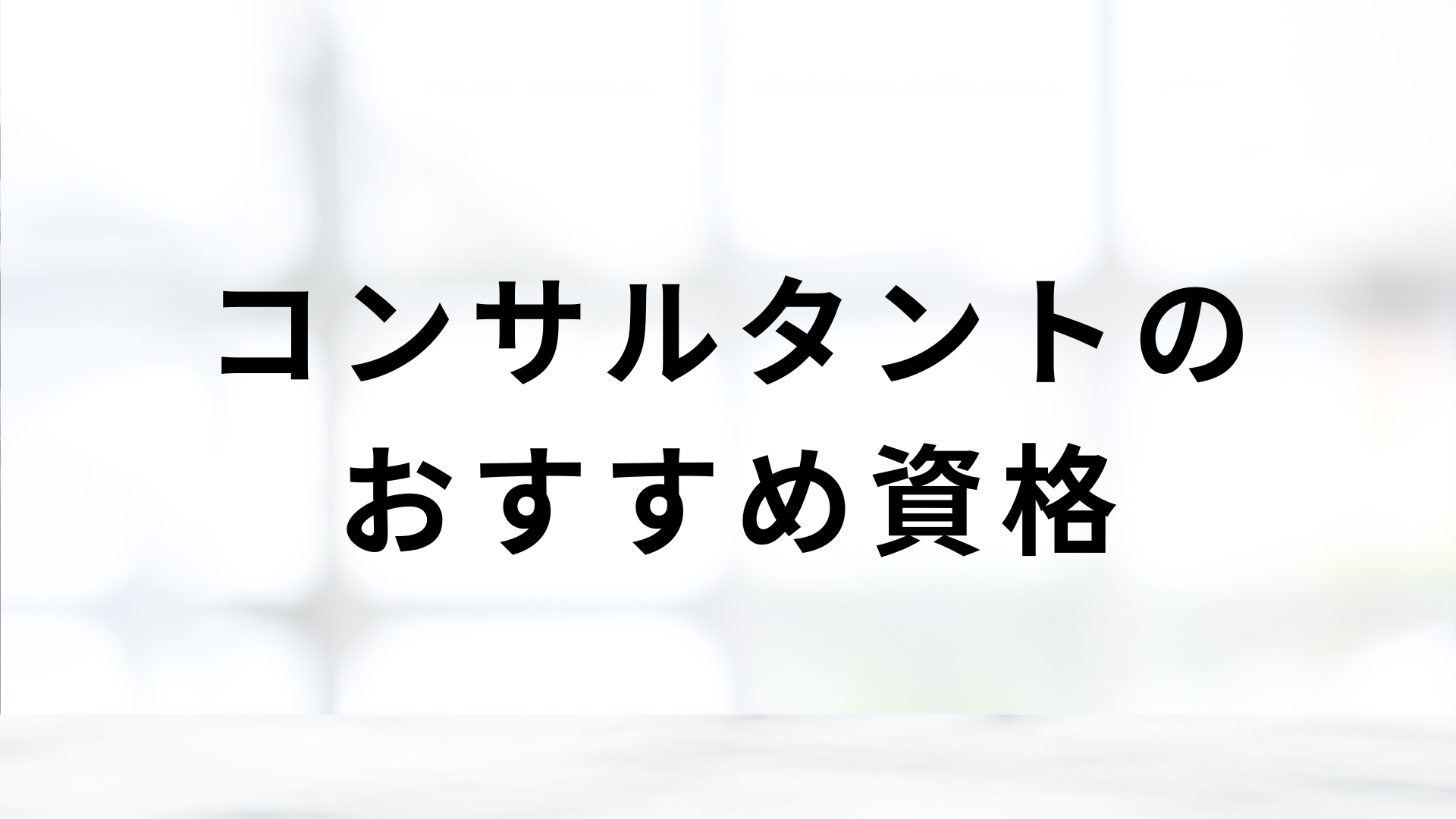






















コメント